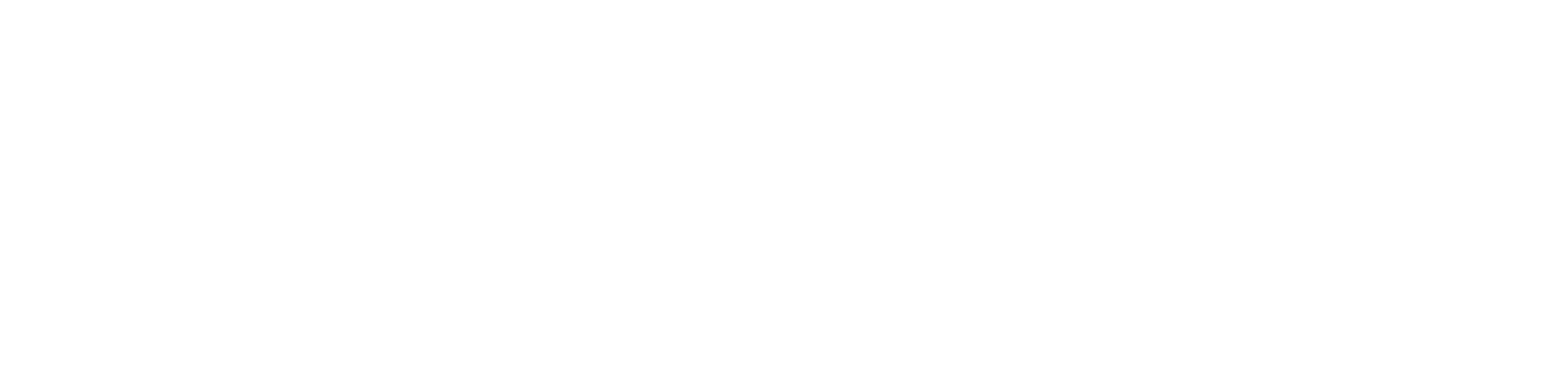日本消音研究所
音の説明
消研は35年来、様々なプロジェクトに対して消音計算書を提供して参りました。ここでは消音計算書に使用される項目や音の基礎知識について、専門外の方にもこ理解頂けるようにこ説明させて頂きます。
そもそも「音」とはなんでしょう?
音とは「空気の振動」と、よく言われます。その振動が鼓膜やマイクに伝わることにより、音として認識されているわけです。その振動のサイクル(周波数・Hz)が速ければ高い音、遅ければ低い音になり、その圧力(デシベル・dB)が高ければ大きい音、低ければ小さい音になります。この周波数とデシベルの組み合わせによって、音は様々な音色として聞こえてくることになります。
では「騒音」とは何か?
聞く人に好ましくない感じを与える音の総称を「騒音」と呼びます。人には主観が有り、聞いた音に対して好ましいか好ましくないかは聞く人が判断していますので、騒音を客観的な物理量によって明確に定義することは不可能に近いと言われています。美しい音楽でも聴きたくない人にはうるさいと感じますし、工事現場の騒音でも、それに慣れてしまった人にはあまりやかましく感じないこともあるようです。このように、騒音とは非常に複雑なものであり、予測を慎重に行う必要が有ります。建築設備に携わる私たちにとっての「騒音」は空調換気系統の室内騒音であったり、ガラリ等からの近隣に対する騒音であったり、室外機やポンプ等の屋外に設置された機械からの騒音であったりします。
単位について
音の高低を表す周波数(Hz・ヘルツ)とは、「1秒間に何回、空気の粗密を繰リ返すのか」を表示しています。 「1Hz」は「1秒間に1回」、「1K(キロ) Hz」は「1秒間に1,000回」の粗密を繰リ返すということです。一般的な成人は「20~20,000Hz」の音を間き取ることができる(可聴域)と言われていますが、加齢によってその範囲は狭くなります。最近「モスキート音(1.7KHz程度の音)を流すことによって若者のたまり場になることを防ぐ」というような話題がありますが、これは20歳程度の人までが聞き取ることができる高周波音を発することによって不快感を与え、長居させないようにする手段の一つになっているのです。残念なことに40代を超えると全く聞き取ることができません。 音の大きさを表すデシベル(dB)は、「人間の耳で聞くことができる一番小さい音(最小可聴値)の圧力を1としたときに、対象となる音の圧力が何倍のものであるのかを対数圧縮して表示しているもの」です。本来であれはその「何倍」という実数を表記すれば良いのですが、非常に大きな数値を使用しなければならないためにわかりづらく、見やすくするためにデシベル値が採用されています。 例えば[3,162,277]という数値があるとします。これは[10の6.5乗]を表したものなのですが、より見やすくするためにその指数を10倍して表記したものがデシベルです。つまり、「最小可聴値の圧力の316万倍の圧力の音圧を65dBと呼ぶ」ということになるわけです。
デシベルの種類
音の大小を計測する騒音計は「Fスケール」「Cスケール」「Aスケール」という3種類の特性を測定できるようになっています。「Fスケール」は純粋に発生している音圧を表示します。「Cスケール」は50Hz以下と5,000Hz以上の周波数域を低めに表示する補正がなされています。これは騒音計内部のセルフノイズや、風などによる雑音の影響を提言する効果があるとされており、一般的な室内騒音の測定に使用されます。「Aスケール」は各周波数域に対して、人間の耳に聞こえる感じのデシベル値に補正(聴感補正)した値が表示され、主に屋外の騒音を測定する際に使用されます。過去に「ホン」と呼んでいたのはこの特性を意味します。 前述したようにデシベルの特性は測定する際に選択する必要が有ります。室内の測定には「FまたはCスケール」、屋外の測定には「Aスケール」をそれぞれ使用しますので気を付けるようにして下さい。
騒音の判定
騒音のレベルを判定する基準には、一般的に「dB」と「NC」の二種類が有ります。
※「dB(デシベル)」
屋外騒音の基準として使用されます。その基準は騒音規制法の下に各行政区が条例として定めておりますので、該 当する地域がどのような定めになっているのかは都度確認する必要が有ります。ここでは参考に東京都の基準を示 します。測定値は四捨五入して整数値で判定します。
| 用途領域 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜間 |
| 6時~8時 | 8時~19時 | 19時~23時 | 23時~6時 | |
| 低層住宅専用地域 | 40 | 45 | 40 | 40 |
| 中高層住宅専用地域 | 45 | 50 | 45 | 45 |
| 商業・準工業地地域 | 55 | 60 | 55(20時~) | 50 |
| 工業地地域 | 60 | 70 | 60 | 55 |
※「NC」
室内騒音の基準として使用されます。部屋の用途によって設計時に決定されますが、指定が無い場合には下記の表を参考にして下さい。63″‘8KHzのどの周波数においてもNC値を下回らねばならないことにこ注意下さい。
| NC値 | 居室の用途(弊社推奨) | 1/1オクターブバンド中心周波数(Hz) | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | ||
| 15 | 録音スタジオ・アナブース・音響実験室 | 47 | 36 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| 20 | 音楽ホール(客席)・撮影スタジオ | 51 | 40 | 33 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 |
| 25 | 音楽ホール(舞台)・多目的ホール・重役室 | 54 | 44 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | 21 |
| 30 | 大会議室・役員室・ホテル客室・病室・映画館・礼拝室 | 57 | 48 | 41 | 35 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| 35 | 会議室・教室・結婚式場・宴会場・ロビー・図書室・美術館 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 34 | 33 | 32 |
| 40 | 事務室・廊下•その他の一般的な居室 | 64 | 56 | 50 | 45 | 41 | 39 | 38 | 37 |
| 45 | 事務室・待合室・研究室 | 67 | 60 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 |
| 50 | 工場内事務室•その他のバックヤード | 71 | 64 | 58 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 |
| 55 | 工場・電算室 | 74 | 67 | 62 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 |
| 60 | 77 | 71 | 67 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | |
| 65 | 80 | 75 | 71 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | |
単位:dB
※暗騒音の影響
対象としている音以外の音を暗騒音と呼びます。機器の運転騒音を判定する際には必ず暗騒音の影響を補正しなければなりません。基本的に機器から発生している騒音は一定ですが暗騒音は変動します。 例えば機器運転時の騒音を測定して53dBであった時の暗騒音が49dBであったとします。一般的に「暗騒音が10dB以上低い場合には無視できる」と言いますが、この場合には4dBの差ですので補正が必要になります。この補正は通常の四則演算ではなく「デシベル値の減算」になりますので関数計算機を必要とします。最近ではエクセル等の表計算ソフトで算出する場合が多いと思いますので、式を書いてみます。
=log10 (1 QA (53[測定結果dB値] /10)-1QA (49[暗騒音dB値] /10))*10単位の項で述べたようにdB値は指数を10倍して表示していますので、測定結果のdB値を10で除します。その指数のべき乗を求めた実数から、同じく暗騒音をべき乗した実数を減じて対数圧縮し、その指数に10を乗じてデシベル表示する。という手順となります。これは減算を加算に転じれば「デシベル和(合成)」に利用できますので参考にして下さい。
消音計算について
弊社が作成している消音計算書に使用されている代表的な項目についてこ説明します。 書中の公式は「空調設備の消音設計(理工学社刊)」より引用させて頂いております。
※消音計算の基礎
全ての消音計算は音圧レベル(SPL)=発生騒音パワーレベル(PWL)+距離減衰(又は放射係数)という基本に基づきます。消音計算書が複雑に見えるのは書中の数値がPWLであったりSPLであったリすることが大きな要素なのですが、どのような計算を行う場合においても、まず騒音源のPWLを求めた上で伝達経路を加味し、最終的な距離減衰又は放射係数(室内環境における反射音を考慮した距離減衰にあたるもの)を加算してSPLを求めねばなりません。流通している消音計算書は玉石混合であリ、この基本が守られていない計算書は論理的に間違いですので、読み手側であるお客様には注意して頂きたい重要なポイントとなリます。 また、ここで敢えて申し上げておきたいのは「消音計算書は架空の数字の羅列である」ということです。メーカーから提供されるPWLに始まり、道中や室内環境における減衰要素はあくまでも推測値にすぎません。正しく分かっているのは消音装置の減衰性能と分配比係数のみであります。消音メーカーの使命は、これらの推測値の羅列を如何にして現実に近い予想騒音に近づけることができるかということに尽きます。消音計算から導かれる結果が唯一無二の正しい結果であるならば、消音メーカー独自の計算方法は無意味であり、画ー的な計算方法が採られるはずです。 しかし、現実には各メーカーから提出される消音計算書の結果は多様であリ、同じ系統を同じように計算しても結果に差が生じます。これはひとえに「消音計算は各社の経験を裏付けにした、それぞれ責任の上に成り立つ予想騒音の算出である」ということなのです。その算出方法の裏側には、膨大な量の計算結果と、それが施工された後の測定結果との照合の歴史がございます。弊社は創業以来この作業を継続しながら、予想騒音と実際の騒音値が整合することを追求しております。
発生騒音パワーレベル(PWL)
音源から発生される「音響出力(W:ワット)」をデシベル表示したものです。耳や騒音計で感じる「音圧レベル(SPL)」ではなく、音源が発生する音のエネルギーを表しています。私たちが設計時の消音計算に使用する送風機のPWLは風量と全静圧から全PWLを算出し、送風機の種類によって周波数特性を加味した演算を行っております。昨今では送風機メーカーから提示される予想PWLを使用することが多くなりましたが、その大小もメーカーによってまちまちですので検証が必要です。また、よく見受けられる間違いとして機器メーカーのSPL値をPWLとして扱ってしまうことがあります。SPLはPWLに測定時の距離減衰を見込んだ値ですから、消音計算の際には必ずその距離減衰の値を加算してPWLに戻さねばなりませんのでこ注意下さい。
※音圧レベル(SPL)
音圧レベル(SPL)=発生騒音パワーレベル(PWL)+距離減衰(又は放射係数)であり、このSPLが耳や騒音計に届 く「音」を意味します。
距離減衰と放射係数
音波は発生すると球体状に拡がる性質を持っています。その性質を根拠に、音源から受音点までの距離を半径とする球の面積分のーを算出したものが距離減衰です。拡がるにつれて音波の密度が薄くなって行くとご理解下さい。
1Olog [Q/4π r2] Q;指向係数,r;距離(m2)[4π r2]は球の面積を求める式ですが、これを分母にして、分子に指向係数を代入することで「何分の一の球面上に音波が拡がるのか」を算出するわけです。無響室と呼ばれるような、反射音の無い環境では一つの完全な球体状に拡がりますのでQ=1。床がコンクリートである半無響室や、床や天井に音源が有る場合は1/2球面へ拡がりますからQ=2、壁と天井の境目のような場所に音源が有る場合にはスイカを1/4に切ったような形状に拡がることになりますのでQ=4となります。本来であれば1/1球面に拡がるはずの音波が1/2や1/4球面にしか拡がらないということは発生した音波の密度が2倍や4倍になるということですから、デシベルの性格上3dBずつ差が出てきます。例えは距離r=1m,指向係数Q=2の場合の距離減衰は△8.0dBですが、Q=4になると△5.0dBになります。このように、音源の位置によって拡散の形状が変化しますので、指向係数(Q)をどのように扱うのかは重要になります。室内の騒音を予測する場合には前述の距離減衰と併せて「室内の反射音」も考慮しなければなりません。音波は15 ℃• 1気圧(1013hPa)のときに約340m/sの速さで進みますから、一般的な居室内部で拡散した場合には直達音とともに壁や天井・床からの反射音も併せて聞こえることになります。対象となる居室の寸法や仕上げにより吸音がどの程度あるのかを加味して吸音による減衰を算出し、直達する距離減衰とを合成したものが放射係数です。
1O lag [Q/4π r2+4/R)] R(室定数)=aΣS/(1-a) a;吸音率, ΣS;室の全表面積(m2)※分配比係数
ダクト系統の消音計算は対象となる居室の特定の制気口までの経路を算出し、最終的に個数を加味して合成しますので、分配比係数が不可欠です。音波が進行方向に向かって分岐するとき、ダクトの断面積に比例して音のエネルギーが分割されますので次式にて算出できます。
1O log [S/ΣS] S;分岐後の計算対象となるダクト面積(m2), ΣS;分岐する総ダクト面積(m2)空調換気系統のダクト面積は通常、通過する風量と比例しますので分配比係数を算出する際には風量比や個数比を使用する場合も多くありますが、近似値として使用に問題は有りません。
※開放端反射
ダクト内を伝播してきた音波が末端の開口から放射されるとき、外部の空気からの反射によって打ち消しあう現象が起きることをいいます。開口寸法が小さいほど低周波域に多くの減衰があり、開口が大きくなるにつれて減衰は少なくなります。弊社の消音計算では開口の形状や周囲の環境に応じて補正した値を使用することがあります。
※ダクトの自然減音
音波がダクト内を伝播する際にはダクトの板振動エネルギーに変換されたり、ダクトから透過したリして相対的な音のエネルギーが減少します。一般的には安全側としてこれを無視することが多いのですが、弊社ではダクト経路が長い場合には消音装置の過剰設置を避けるため、直管ダクト長1mあたり△0.3-0.SdBにて計算することがあります。また、曲管部では高周波域での減衰が大きくなる傾向がありますが、弊社では全体の経路を鑑みた上で調整した値を使用することがあります。
※各種の再発生騒音
弊社は30数年来、空調機や送風機のPWLから末端の制気口までの経路を計算して参りましたが、過去にはPWLから道中の減衰要素を減じて計算結果とし、許容騒音との差をもって必要減衰量とする計算が主流でした。この計算方法の欠点は道中におけるダンパや器具等の再発生騒音を考慮しないことにありました。NC-20を目標とするような居室などは、この再発生騒音によって問題が生じることが少なくありません。弊社では総合的な観点から、ダクト寸法やダンパの位置、並びに器具の形状や寸法等についても問題点として提起します。
・ダンパの再発生騒音
PWL=L0 + 1 O logA+SSlogVPWL;気流騒音のオーバーオールPWL
V;ダクト内の平均風速(m/s),A;ダクト断面積(m2)
L6;ダンパの羽根角度(0)によって定まる定数(dB)
・器具の再発生騒音
PWL=101ogA+a • logV+bPWL;気流騒音のオーバーオールPWL
V;制気口面風速または首風速(mis)
A;制気口断面積または首面積(m)
a,b;制気口の種類こ‘とに実験的に定められる定数(dB)
これらのオーバーオールPWLから周波数ことの相対値を加味して算出されます。弊社では過去の実例から鑑み、定数を見直しながら現実感に即した計算を行っております。
※ダクトからの透過音
それぞれの制気口からの騒音を算出して合成した結果をもって対象となる居室での予想騒音とする計算方法が主流であった20余年前から、弊社が提起し始めたのが「ダクトからの透過音」です。 ダクト経路の下にある居室においては、制気口が無くても低周波騒音が問題になることが良くあります。これが透過音による問題であることをいち早く指摘し、その計算方法を確立してきたのも弊社です。解決方法も多岐にわたるため、弊社では画ー的な対策のこ提案は致しません。お客様のこ希望を伺いながら、それぞれのケースに最適となる方法を策定させて頂いております。また、現在に至っても測定結果から計算方法を見直す作業を継続し、より正しい予想騒音の算出を追求しております。
※機械室からの透過音
機械室の隔壁が乾式になって久しいですが、それに伴って壁からの透過音の問題が顕在化して参りました。日を追うに連れて機械室は小さくなり、居室に近づいています。また、機械室が広い場合・狭い場合、空調機が壁に近い場合・遠い場合、それぞれの音の拡がり方には差異があります。弊社ではダクト系の騒音のみならず、機械室壁からの透過音に対しても様々な計算方法を考案しております。それぞれのプロジェクトのそれぞれの居室の状況は千差万別です。建築と設備の両面から問題に向き合い、プロジェクト全体が整合性をもって問題を解決するお手伝いに力を注ぎたいと考えております。